「家業を継ぐために会社を辞めたいけど、どう伝えればいいの?」「退職理由って正直に言って大丈夫?」そんな悩みを抱える方は意外と多いんです。親の引退や事業継承のタイミングなどで決断する人が増えている今、家業を理由に退職することは特別なことではありません。ただし、誤解なく、そして円満に退職するには“伝え方”がとても大切です。本記事では、家業継承に伴う退職理由の例文やマナー、メッセージの書き方まで徹底解説します。
- 家業継承による退職が増えている背景と現代的な理由を解説
- 上司・同僚・社外向けの退職理由の伝え方と例文を完全収録
- 円満退職に欠かせない心構えとNG例を紹介
- 実際の引き継ぎ準備や生活設計の具体的なポイントも解説
家業を継ぐために退職する人が増えている理由
家業を理由に会社を辞めるという選択肢は、かつては「特殊な事情」と見なされがちでした。しかし最近では、親の高齢化や事業承継の重要性が認知されるようになり、むしろポジティブなキャリア選択と捉えられることが増えてきています。ここでは、その背景にある時代の流れや社会的な変化について見ていきましょう。

社会的背景と時代の変化
少子高齢化や地方の過疎化が進むなか、家業を継ぐことは地域社会や日本の産業構造を維持するためにも重要な役割を担っています。中小企業庁の統計によると、2023年時点で60歳以上の経営者が約半数を占め、10年以内に事業承継が必要な企業が急増しているといいます。
こうした流れの中で「家業を継ぐために退職する」という決断は、もはやマイノリティではなくなってきているのです。親からの強い要望や地域社会への貢献意識、また「自分で事業を動かしたい」という主体的な理由から継承を決意する人も増えています。
親の高齢化・事業承継の現実
親世代が高齢化し、現場に立てなくなる時期が近づくにつれ、家業継承の必要性は現実味を帯びてきます。「急に体調を崩した」「跡取りがいないと取引先が不安視する」といったプレッシャーも、子ども世代の決断を後押しする要因です。
また、家業が家族や親族にとって生活の基盤になっている場合、それを維持する責任感も大きな動機になります。こうした背景から、ある程度のキャリアを積んだ30代〜40代での転機として選ばれるケースが多く見られます。
自己実現とライフスタイルの変化
家業を継ぐことが単なる義務ではなく、「やりたいこと」「新たな挑戦」として捉えられる時代になってきています。自分らしい働き方や地域とのつながり、スモールビジネスの魅力を再評価する動きも後押ししています。
とくに都市部で働くサラリーマンの中には「毎日の通勤に疲れた」「もっと家族との時間を大切にしたい」と感じる人も多く、地方での家業に携わる暮らしに魅力を感じて転身を決意するケースも。単に“親の跡を継ぐ”だけでなく、“新しい生き方の選択”としてポジティブに捉えられているのが今の潮流です。
家業を継ぐ退職理由の伝え方【基本マナーと心構え】
退職理由を「家業を継ぐため」と伝える場合、一見納得されやすい理由に思えますが、伝え方次第で印象は大きく変わります。上司や同僚に不信感を与えたり、トラブルのもとになったりしないように、適切なマナーと心構えを持つことが大切です。ここでは、具体的な場面ごとの伝え方や注意点、円満退職につながるコツについて解説します。
面談・書面・メールそれぞれの伝え方
まず退職の意思を伝える基本は「口頭での面談」です。直属の上司に時間を取ってもらい、落ち着いた環境で丁寧に伝えましょう。「実家の家業を継ぐため、退職を決意しました」と、結論から話すのがポイントです。その際、曖昧な説明は避け、家族内での事情や将来の展望など、可能な範囲で具体的に伝えると誠実な印象になります。
面談後、正式に退職届を提出します。こちらには簡潔に「一身上の都合により退職いたします」と書くのが一般的ですが、必要に応じて「家業承継のため」と補足するケースもあります。
社外や部署が離れている関係者にはメールで伝えることもありますが、この場合も冒頭で感謝を述べ、家業継承という前向きな理由であることを明確に伝えるようにしましょう。
円満退職につながる言い方のポイント
「できるだけ迷惑をかけずに辞めたい」「引き継ぎもきちんとしたい」など、周囲への配慮の気持ちを伝えることが、円満退職の鍵になります。また、「前から家業のことで相談していた親が体調を崩した」など、家業に関わる背景がある場合は率直に説明しても構いません。
「やりたくない仕事を逃げるために辞めるのではなく、新しい役割を引き受ける」という姿勢を示すと、誠実で前向きな印象を与えることができます。逆に、職場や業務への不満を理由に見せると、協力的な空気が生まれにくくなるので要注意です。
また、送別会や最終出勤日などの挨拶では「在職中にお世話になった感謝」と「今後の意欲」をセットで話すことで、良い印象を残せます。「これからも社会人として恥じないよう、精進します」といった一言も効果的です。
NGな言い方・トラブル事例
どんなに事情があっても「もう限界なので」「正直、この会社に将来性がないと感じた」といったネガティブな表現は絶対に避けましょう。家業を理由にした退職は理解されやすい反面、「建前じゃないか?」「本当は転職するのでは?」と勘ぐられる場合もあります。
特に社内SNSやLINEで感情的に発言したり、退職理由と矛盾する投稿をすることは信頼を損なう大きなリスクです。「後継ぎをやると決めたので、ここでの経験を活かして頑張ります」と、今の職場にも敬意を払う姿勢を忘れないようにしましょう。
また、退職後すぐに他社で働き始めたり、まったく別業界でSNSを更新したりすると、「あれ、家業って言ってたのに?」と不信感を与える原因になります。実際には転職の場合でも、最初の説明と行動に一貫性を持たせることが円満退職のコツです。
退職理由を伝える例文集【目的別】
ここでは、実際に家業を継ぐ理由で退職する場合に使える例文を、社内(上司・同僚)向けと社外(取引先など)向けに分けて紹介します。口頭・メール・挨拶状など、用途別にすぐ使えるフレーズを厳選しました。言い回しに悩んだときの参考にしてください。
社内(上司・同僚)への伝え方
口頭での例文
「お忙しいところ、お時間をいただきありがとうございます。私事で恐縮ですが、実家の家業を継ぐことになり、退職を決意いたしました。家族とも話し合いを重ね、私が後を引き継ぐべきだと判断いたしました。これまで多くのことを学ばせていただき、大変感謝しております。できる限りご迷惑をおかけしないよう、業務の引き継ぎも責任を持って対応いたします。」
このように、結論→理由→感謝→引き継ぎの順で話すことで、誠実な印象を与えることができます。
メールでの例文
件名:【退職のご挨拶】◯◯部 ◯◯より
◯◯部長
いつも大変お世話になっております。突然のご連絡となり恐縮ですが、私、◯◯は◯月末をもって退職することとなりました。理由といたしましては、実家の家業を継ぐことが決まり、家族と相談のうえ決断いたしました。
在職中は多くの学びと経験を得ることができ、本当に感謝しております。ご迷惑をおかけしないよう、残りの期間も業務に全力で取り組み、引き継ぎにも責任をもって対応いたします。何卒よろしくお願い申し上げます。
◯◯ ◯◯
社外(取引先・関係者)への挨拶例文
退職挨拶状の文例
拝啓 盛夏の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、私こと、このたび実家の家業を継ぐこととなり、◯月◯日をもちまして◯◯株式会社を退職する運びとなりました。在職中は一方ならぬご厚情を賜り、心より御礼申し上げます。
今後は家業の発展に尽力し、これまでの経験を活かしてまいります。何卒変わらぬご指導とご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。
末筆ながら、貴社の益々のご繁栄と皆様のご健勝をお祈り申し上げます。
敬具
メール・LINEでの挨拶例文
件名:【退職のご挨拶】◯◯株式会社 ◯◯より
〇〇様
いつも大変お世話になっております。突然のご報告となり恐縮ですが、私◯◯は◯月末をもって退職することとなりました。理由は、実家の家業を継ぐこととなったためでございます。
在職中はご指導、ご鞭撻を賜り、誠にありがとうございました。短い間でしたが、非常に充実した時間を過ごすことができました。引き継ぎにつきましては、後任の◯◯が対応させていただきますので、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。
末筆ながら、皆様のますますのご健康とご活躍をお祈りいたします。
◯◯ ◯◯
家業継承に向けた準備と心構え
退職して家業を継ぐことは、単に仕事を変える以上に「人生の転機」となる大きな決断です。家族や親族、取引先や従業員との関係性、経営や財務に関する知識など、準備しておくべきことは多岐にわたります。後悔のない選択にするためにも、継承前にやっておきたいこと・考えておきたいことを整理しましょう。
実際に必要な引き継ぎ準備とは?
まずは現経営者である親や家族から、業務内容・資産状況・経営戦略・取引先情報などを詳細にヒアリングすることが不可欠です。事業の実態を正確に把握しなければ、いざ引き継いだ後に想定外のトラブルが起こることも。
加えて、経理や法務、人事、IT管理といった裏方業務の流れも確認しておきましょう。役所や商工会議所への届け出、各種名義変更など、事務的な作業も意外と多く時間がかかります。退職前にある程度準備を進めておくと、スムーズなスタートが切れますよ。
親族との話し合い・スケジュール策定
家業継承は「家の問題」であると同時に、「事業の継続」という社会的責任も伴います。兄弟姉妹や配偶者、親族など、関係する全員と事前に話し合い、今後の方向性や役割分担を明確にしておくことが大切です。
継承のタイミングや準備に必要な期間をあらかじめスケジューリングし、計画的に退職や引き継ぎが行えるように調整しましょう。また、親世代との価値観の違いや経営判断のズレがある場合も、早めにすり合わせておくと後々の衝突を防げます。
事業計画と生活設計を両立させる
継ぐことが決まったら、最低限の事業計画(中期ビジョン・収益見込み・課題抽出)を自分なりに立てておくのがおすすめです。それに加えて、生活費・住居・家族のライフスタイルなど、自分自身の生活設計もセットで考えましょう。
収入が不安定になる時期があれば、その間をどう乗り切るか、貯金や副収入のシミュレーションも必要です。家業継承は気持ちだけで成り立つものではありません。現実と向き合いながら、一歩ずつ準備していくことで、安定した継承が実現できます。
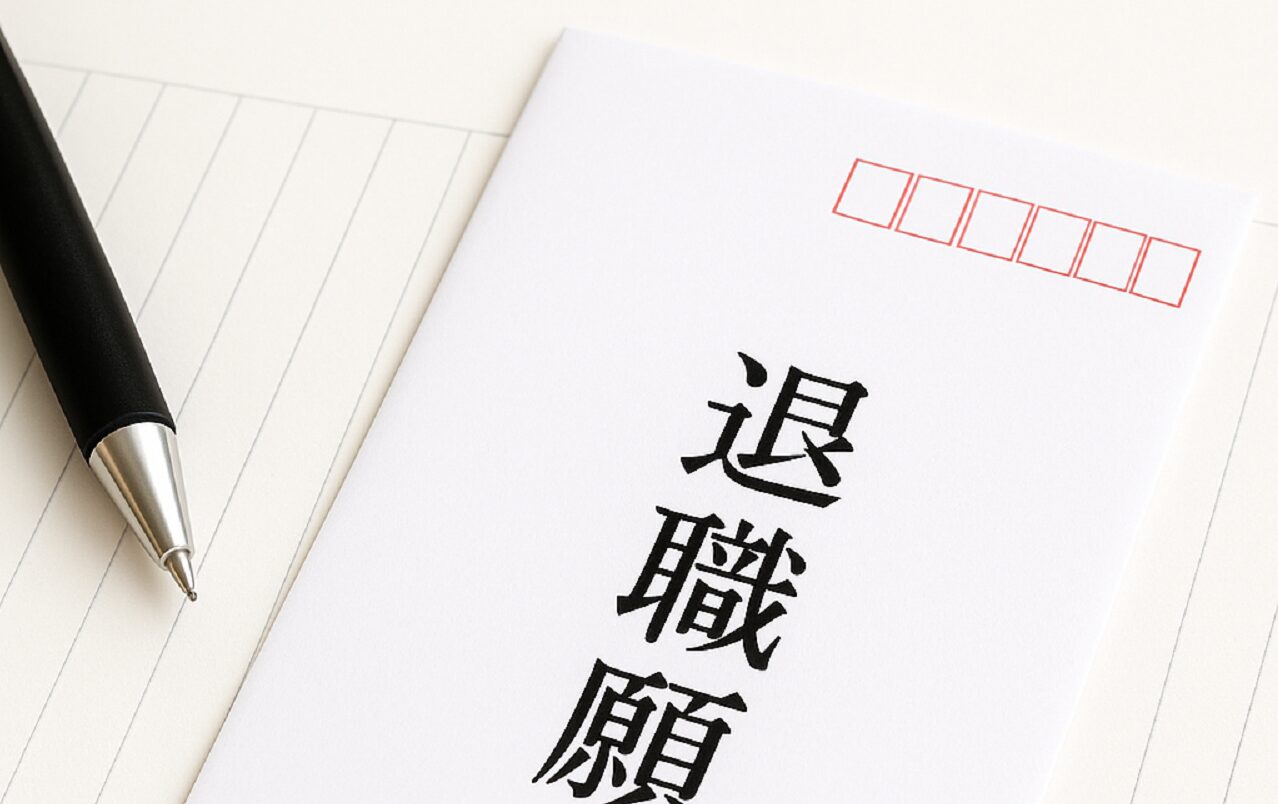
Q&A:よくある疑問とその回答
ここでは、「家業を継ぐために退職する」ことに関してよく寄せられる質問をまとめました。不安をひとつひとつ解消して、安心して新たな一歩を踏み出しましょう。
- 退職理由に「家業を継ぐ」と言えば引き止められない?
-
比較的引き止められにくい理由の一つですが、伝え方やタイミングによっては「もう少し頑張ってみては?」と言われることもあります。大切なのは、家族と相談して決断したこと、事業の必要性があることなどを誠実に伝えることです。迷いなく決意を伝えれば、周囲も応援してくれるでしょう。
- 本当は転職だけど「家業を継ぐ」と嘘をついても大丈夫?
-
一時的には便利に思えるかもしれませんが、後で矛盾が出ると信用を失うリスクがあります。特にSNSや人づてで新しい職場が判明する可能性もあるため、なるべく正直に「家庭の都合」など柔らかい表現を使うのが無難です。誠実な対応が円満退職への近道です。
- 家業を継ぐと決めたけど不安…どう乗り越える?
-
不安はあって当然です。家族とよく話し合い、第三者のアドバイス(商工会議所、士業、先輩経営者など)を受けるのもおすすめです。最初から完璧を目指さず、まずは「事業を知る」「周囲と信頼を築く」ことから始めましょう。準備期間をしっかり取れば、確実に前に進めます。

自分や家族のための大きな決断だからこそ、しっかり準備して丁寧に伝えましょう!円満に退職できれば、家業も気持ちよくスタートできますよ。











