「音楽で食べていけたら最高なのに…」そんな夢を抱いたこと、一度はありませんか?でもSNSやネットでは「音楽業界はやめとけ」と警鐘を鳴らす声が多数。華やかに見える世界の裏側には、想像以上に過酷な現実があるのも事実です。
本記事では、なぜ“やめとけ”と言われるのか、その理由と乗り越え方、辞めた人のその後まで、音楽業界に関わるすべての人に届けたいリアルな情報を徹底解説していきます。
- 音楽業界が「やめとけ」と言われる5つの理由を現場目線で解説
- 成功する人の特徴と、続ける価値がある条件も紹介
- 異業種への転職例や“音楽を辞めた人のその後”も具体的に掲載
- 「辞めたら負けじゃない」自分軸で選ぶための判断材料を提供
音楽業界は「やめとけ」と言われる理由とは?

「音楽業界に入りたい」「音楽で生きていきたい」と思っても、現実は甘くない──。そんな警告のようなフレーズ「音楽業界はやめとけ」が検索される背景には、華やかなイメージとは真逆の厳しさがあります。実際に働く人々の声やデータをもとに、“なぜやめとけと言われるのか”をひも解いていきましょう。
音楽業界に夢を見る人が多いのはなぜか
「音楽の仕事ってかっこいい」「いつか自分の曲がヒットして、有名アーティストになりたい」──そう思ったことがある人、多いですよね。音楽業界って、やっぱり憧れの対象なんです。小さい頃にテレビで見たスターや、ライブで心を揺さぶられた経験から、「自分もこんな風になりたい」と思うようになるのは自然なこと。
また、音楽そのものが“感情に訴える芸術”なので、聴く人の心に強く残ります。そういった影響から、音楽を届ける側に立ちたいと考える人が後を絶ちません。そして最近ではSNSやYouTubeなど、自分の作品を発表しやすくなったことも追い風に。バズる=成功というイメージも広まり、「自分もいけるかも」と感じやすいのです。
もちろん、音楽が好きという純粋な気持ちが出発点になるのはとても大事なこと。でもその一方で、“好き”だけでは立ち行かない現実も待っています。音楽業界は、ただの憧れや理想だけではやっていけないという声があるのも事実。だからこそ、ここからはその「ギャップ」に向き合っていきましょう。
幼少期からの憧れと「好きなことを仕事に」
「歌手になりたい!」「ギターで食べていきたい!」──そんな夢を語ったこと、子どものころにありませんでしたか?音楽に限らず、誰しも一度は“好きなことを仕事にできたらいいな”と思うもの。そして音楽業界には、その夢を追いかけるスタートラインに立つ人が多くいます。
たとえば、幼少期からピアノを習っていたり、学生時代に軽音部でライブを経験したりと、音楽と共に育ってきた人にとっては、その延長線上に“音楽の仕事”があるように感じるんですよね。「誰かの心を動かす仕事がしたい」「自分の表現で人を救いたい」そんな純粋な気持ちが原動力になって、音楽業界に飛び込む人はとても多いんです。
もちろんその気持ちは尊いし、大事にすべき。でも、現実は“好き”だけでは続けられない。たとえば、深夜までの制作や、報酬のないライブ出演、評価されない苦労が日常茶飯事。そこに理想とのギャップを感じてしまう人も多いのが現実です。「好きなことを仕事にする」という言葉の裏には、強い覚悟と現実を受け入れる力が必要なのかもしれません。
メディアやSNSによるキラキラした成功例の影響
テレビやYouTube、SNSで見る音楽アーティストたちって、本当にキラキラして見えますよね。「あの人、TikTokでバズってメジャーデビューしたらしいよ」「YouTubeの再生数が数百万回って、すごくない?」と、成功者のストーリーがたくさん拡散される時代。確かに夢があります。でも、それってほんの一握りのケースなんです。
たとえばバズった動画の裏には、何十本、何百本と再生されなかった投稿があります。多くの人が結果が出るまでに時間をかけ、見えないところで努力と失敗を繰り返しているんです。でもSNSのタイムラインでは、結果だけが切り取られて流れてきます。「あの人にできたなら、私もいけるかも」と思う気持ちは自然。でもその陰には、目に見えない犠牲や挫折があることを忘れてはいけません。
メディアもSNSも“光の部分”を強調する傾向があるため、業界のリアルな厳しさが伝わりづらくなっています。成功した人が「私は苦労しました」と語っていても、それすらも輝かしく聞こえてしまうほど。でも実際には、「光」を浴びるまでに心をすり減らして業界を去った人が、もっとたくさんいるんです。音楽業界で生きていくには、その現実も知った上で、覚悟を持って飛び込むことが大切なんです。

現実は過酷?「やめとけ」と言われる5つの理由
「夢のある世界」と思われがちな音楽業界ですが、実際に足を踏み入れると想像以上に厳しい現実にぶつかります。なぜここまで「やめとけ」と言われるのか、その理由には多くの人がつまずいた“壁”が存在します。以下では、代表的な5つの理由について掘り下げていきます。
- 労働時間が異常に長い
- 報酬が少なく、生活が成り立たない
- 実力よりコネや運が優先される
- 人間関係や競争がストレスになる
- 安定性が低く、将来の不安が大きい
1. 労働時間が長すぎる(休みが取れない)
音楽業界に入ると、まず最初に驚くのが“時間感覚のなさ”です。レコーディング、ライブ準備、イベント運営、アーティスト対応…とにかくやることが山ほどあるのに、人数が少ない現場では一人あたりの業務量がとても多くなります。拘束時間は長く、早朝から深夜まで働くことも珍しくありません。
たとえば音楽イベントやライブハウス関係では、リハーサルから本番、撤収作業まで一日中拘束されることが多く、週末や祝日など“普通の人が休む日”こそが稼働のピークです。つまり、一般的なカレンダーどおりの休日がほとんどなく、「何ヶ月も休みなし」なんて話も珍しくありません。
しかも、これだけ働いても残業代が出ないケースが多いのが現実。音楽業界は「夢」や「やりがい」を理由に、労働環境が軽視されがちです。「好きでやってるんでしょ?」という空気のなか、正当な対価が支払われない働き方に疑問を感じて辞める人も多いです。
「本当に音楽が好きだから頑張れる」と思っていても、体や心が悲鳴をあげたとき、それは“夢の代償”では済まされません。労働時間の長さは、夢を追う若者の健康や将来を脅かす大きな問題なんです。

2. 薄給・無報酬も珍しくない
「音楽の仕事って儲かるんじゃないの?」そんなイメージを持たれがちですが、実際はまったく逆。音楽業界では“好きだから”という理由で、報酬が極端に低かったり、そもそも無報酬の案件も多く存在します。
たとえば新人アーティストやインディーズの現場では、「勉強だから」「経験になるから」といった理由で、交通費すら出ないボランティア参加が当たり前のように行われています。音楽制作に関わるスタッフも、駆け出しのうちは1曲あたり数千円レベルの報酬しかもらえないこともあり、時給換算すると数百円以下ということもざらです。
もちろん、メジャーな現場や売れっ子のスタッフになればある程度の報酬は得られるかもしれません。でも、そこに到達できるのはほんの一握り。ほとんどの人は「好きなことで生活ができない」現実にぶつかり、他の仕事と掛け持ちしながら音楽活動を続けるのが実態です。
「これで食べていけるのか?」という不安を常に抱えながら働く環境は、精神的にも大きなストレスになります。夢を追う一方で生活がままならず、最終的に音楽から離れざるを得ないケースも少なくありません。
3. コネと運がものを言う世界
音楽業界においては、実力や努力だけではどうにもならない現実が存在します。それが「コネ」と「運」です。「誰と繋がっているか」「どのタイミングで出会えるか」が、キャリアを大きく左右する場面が本当に多いんです。
たとえば、実力が同等の二人がいたとして、片方が業界人と親しい関係を築いていれば、ライブの出演や仕事のチャンスが一気に広がることもあります。また、有名アーティストのサポートやテレビのタイアップなど、突発的な“運”の要素で一気にブレイクする例もあり、「チャンスをつかめたかどうか」が命運を分けることも。
もちろん、努力して人脈を広げたり、SNSで発信を続けて自分を売り込むことも大切。でも、そうした努力が報われるとは限らないのが音楽業界の厳しさです。むしろ「なぜあの人が選ばれて、自分は選ばれないのか」と理不尽さを感じてしまうこともあります。
この「実力主義ではない部分」に心が折れてしまい、やめていく人も多いのが実情。才能や情熱があっても、“コネがないから” “タイミングを逃したから”という理由で埋もれてしまう世界。それが、音楽業界が「厳しい」と言われる大きな理由のひとつなんです。
4. 精神的に消耗する人間関係と競争
音楽業界は「人とのつながり」がとても重要な世界。でもそれが、逆にストレスの原因になることも少なくありません。アーティスト同士、スタッフ間、事務所との関係など、独特な上下関係や気を遣う場面が多く、精神的にかなり消耗します。
たとえば、ライブハウスでの出演枠をめぐる“暗黙の争い”、レーベル内でのライバル関係、作曲家やアレンジャー同士の仕事の取り合いなど、表には出ないけれど裏では激しい競争が繰り広げられています。しかも、「仲良くしなければ次のチャンスがもらえないかもしれない」という不安があるため、表面上は笑顔でも内心はギスギス、という状況もしばしば。
さらに厄介なのが、実力主義ではないがゆえに、評価基準があいまいなこと。「なぜあの人ばかりが評価されるのか」「自分は見てもらえないのか」と感じると、自信を失いやすく、メンタルがすり減ってしまいます。人間関係に疲れ、業界を去る人が多いのも、このストレスの大きさが関係しています。
「音楽が好き」「人とつながるのが好き」と思って入ったはずなのに、人間関係で傷ついて辞めてしまう…。そんな矛盾した結末にならないためにも、自分の心を守る意識はとても大切です。

5. 将来が見えにくい不安定な業界構造
音楽業界は、華やかな世界の裏で非常に不安定な構造になっています。売れるか売れないかで人生が180度変わるような環境で、安定したキャリアプランを描くのがとても難しいのが実情です。
たとえば、レーベルに所属しても売上次第では簡単に契約が打ち切られることがあります。インディーズで活動する場合も、収入源がライブやCD、グッズなどに偏っており、コロナ禍のようなイベント中止が一気に生活に直結するリスクがあるのです。サブスクの普及によって音楽単価が下がり、1再生あたりの報酬はわずか数円〜数十銭。再生数だけでは生活できません。
さらにテクノロジーの進化により、AI作曲や自動マスタリングなどが登場し、従来のスキルが通用しなくなる可能性も出てきています。どれだけ努力しても、業界そのものの仕組みやルールが変わってしまえば、個人の力ではどうにもならない部分も多いんです。
そんな中で、「10年後、20年後も音楽業界で食べていけるか?」と問われると、明確な答えを出せる人はごくわずか。将来設計がしづらく、不安定な状況に耐えられずに辞めていく人が多いのも納得です。夢だけでなく、現実としての“生きていく手段”として、音楽業界を見つめ直すことが求められています。

それでも音楽業界に残るべき人とは?
ここまで読んで「やっぱり音楽業界は無理なのかも…」と感じた方もいるかもしれません。でも、すべての人にとって向いていないというわけではありません。現実が厳しいのは事実ですが、それでもこの業界で夢を実現し、自分らしく生きている人もたくさんいます。
では、どんな人が音楽業界で“やっていける”のか。その特徴や共通点を知っておくことで、自分に向いているのか、今後どう進むべきかのヒントが見えてくるはずです。このセクションでは、「残るべき人」「続ける価値のある人」の特徴を紹介していきます。
音楽業界で成功している人の共通点
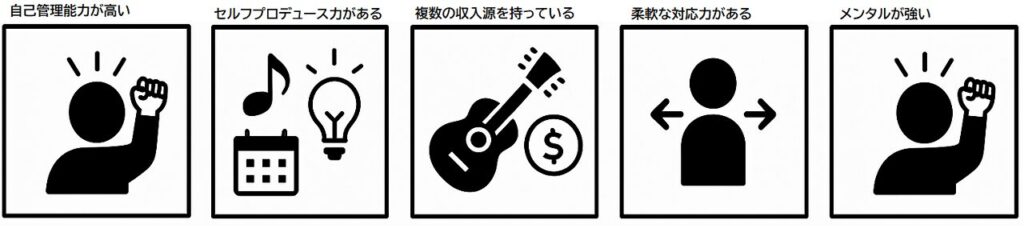
音楽業界で長く活躍している人たちには、いくつか共通する特徴があります。それは「才能」や「運」だけではなく、環境に左右されずに自分を成長させられる“地力”です。成功している人は、その都度起きる問題や変化に対して、柔軟に対応できる力を持っています。
たとえば、音楽制作だけでなく、SNSや動画編集などにも精通し、セルフプロデュースができる人。自分の魅せ方を理解して、発信力を持つことでチャンスを自らつかみに行くタイプの人は、業界内外問わずに強い存在感を発揮します。
また、「一つの収入源に依存しない」のも大きなポイント。ライブ、グッズ販売、作曲提供、サブスク、YouTube、ファンコミュニティなど、多角的に収入を得る仕組みを構築している人は、時代や環境の変化にも対応しやすくなります。
そして何よりも共通しているのは、「自分自身を信じ続けるメンタルの強さ」です。評価されない時期や売れない時期を乗り越えた人ほど、地に足のついた考え方を持っていて、表面だけのキラキラではない“本物の強さ”を感じさせます。
高い自己管理能力とセルフプロデュース力
音楽業界で生き残るには、何より「自分をマネジメントできる力」が不可欠です。売れっ子でなくても、自分の活動をスケジュールし、体調を整え、情報発信を定期的に行う。この基本をしっかり回せる人は、信頼もされやすくチャンスも広がります。
たとえばSNSの活用。定期的に投稿し、ファンとのコミュニケーションを大切にすることで、フォロワーが増えたり、思わぬコラボの話が来たりします。ただ待っているだけでは何も起こりません。自分を「プロデュースする力」がある人は、音楽以外の場でも活躍しやすいんです。
また、スケジュール管理や金銭感覚もとても大事。寝不足や生活の乱れはパフォーマンスにも影響しますし、無理な投資や活動で赤字を出し続ければ、心身の限界が来るのは時間の問題。逆に、地に足のついた生活設計ができる人ほど、長く活動を続けられます。
「好きなことを仕事にする」って、自由で楽そうに見えるかもしれません。でも実際は、誰にも守ってもらえない分、自己管理がものを言う世界。そこを乗り越えられる人が、音楽業界での成功に近づけるんです。
複数の収益源を持つなどの経済的自立
「音楽だけで食べていくのは難しい」──この現実を理解した上で、複数の収入の柱をつくっている人は、やはり強いです。たとえば、楽曲提供やライブだけでなく、YouTubeの収益、配信アプリでの投げ銭、講師業、サブスク配信、クラウドファンディングなど、多様な手段で自分の活動をマネタイズしています。
このように複数の収益源を持っていると、たとえ一つのルートが止まっても他で補えるため、精神的にも余裕が持てます。たとえば「ライブが急に中止になった」「案件が飛んだ」という時でも、他の手段がある人は立て直しやすいんです。
また、収益源を分散することで、自分の可能性や適性にも気づけます。「音楽しかやりたくない」と思っていた人が、発信活動を続ける中でライティングや動画編集のスキルを活かす道に進むことも珍しくありません。音楽に軸足を置きながらも、新しい価値を生み出せる人ほど、柔軟でしなやかなキャリアを築いています。
「売れるまで我慢」の一本勝負ではなく、「自分の活動を持続可能にする仕組みづくり」が、これからの音楽人生には欠かせない要素なのかもしれません。
続ける価値がある人の3つの条件
音楽業界がどれだけ厳しくても、「続ける価値がある人」はたしかに存在します。ここで言う“価値”とは、単に売れる見込みがあるとかではなく、「音楽を続けることで人生が豊かになるかどうか」という視点です。以下の3つに当てはまるなら、あなたには音楽を続ける力と理由があるかもしれません。
- 自分をブランド化できる人
- 音楽以外にも興味・知識を広げられる人
- 他人の評価より自分の意思を優先できる人
自分をブランド化できる
現代の音楽業界では、ただ「いい曲が作れる」「歌がうまい」だけでは足りません。大切なのは“あなたにしかない個性”を明確にして、それを発信し続けること。つまり、「自分自身がブランド」として認知されることが、活動を続ける上で大きな武器になるのです。
たとえば、音楽だけでなくライフスタイルや価値観、ビジュアル、話し方などを含めた「世界観」をSNSやYouTubeで発信することで、共感してくれるファンが自然と集まってきます。「〇〇っぽい世界観が好き」という指名買いが起きれば、無理に売り込まなくても、音楽が届くようになります。
「音楽業界で生き残る=自分の魅力をどう届けるか」。この考え方を持ち、セルフプロデュースの意識を高く持てる人は、自然と業界内外から声がかかる存在になっていきます。自分をブランド化できるかどうかが、分かれ道になるとも言えるでしょう。
音楽業界を辞めた人の「その後」とは?
音楽業界を辞めた人は、その後どんな道を歩んでいるのでしょうか?「辞めたら終わり」と思われがちですが、実際には音楽業界で培ったスキルや経験を活かして、異業種で活躍している人もたくさんいます。このセクションでは、よくある転職先や、意外な相性の良い業界をご紹介します。
音楽業界から異業種への転職例
音楽業界で身につけたスキルや感性は、実は他業種でも重宝されることがあります。たとえば、音楽ディレクションやイベント運営、デザインやプロデュース力など、マルチな能力を持つ人は思いのほか多く、異業種に転職して成功している例も多数存在します。
IT業界やマーケティング業界に強い親和性
音楽業界経験者は、ITやマーケティング業界にスムーズに転職できることがあります。なぜなら、SNS運用・YouTube戦略・データ分析・企画立案など、音楽活動で自然に行ってきたことが、マーケティング職やWebディレクター職に直結しているからです。
たとえば、バンドのプロモーションやイベント集客で鍛えた「見せ方」や「発信力」、またスケジュール管理やクリエイティブな思考は、ベンチャー企業や広告代理店でも重宝されます。実際に「音楽→Web制作」や「音楽→SNS運用」への転身事例は年々増えており、未経験でもポテンシャル採用されるケースもあります。
音楽のスキルを活かせる教育・福祉分野も
また、音楽そのもののスキルを活かして、教育・福祉分野へ転職する人もいます。音楽教室の講師や、子ども向けリトミック指導、療育施設での音楽支援など、音楽を通じて人と関わる仕事は意外と多いんです。
とくに音楽療法(ミュージックセラピー)は、近年注目が高まっており、高齢者施設や医療現場でのニーズも拡大しています。「音楽が人を癒す力」を信じていた人にとっては、転職後も音楽の本質に関われる仕事と言えるでしょう。華やかさはなくても、人の役に立てるという意味ではやりがいを感じられる分野です。
転職で後悔しないためにやるべきこと
音楽業界を離れる決断をしたとき、次に不安になるのが「転職で失敗したらどうしよう」ということ。確かに、長年音楽に打ち込んできた人ほど、一般的な職歴やスキルに自信が持てないこともあるかもしれません。でも、実は音楽で培ってきた力は、きちんと棚卸しをすれば立派な“武器”になります。
ここでは、音楽業界からの転職で後悔しないために、今すぐできる準備と、サポートを受ける方法についてご紹介します。転職活動は「段取りと情報戦」。焦らず、でも確実に前に進んでいきましょう。
自分の強み・スキルを可視化する
まず大事なのは、自分の「できること」を整理することです。たとえば、「ライブ企画が得意」「SNSでフォロワーを伸ばした経験がある」「期限内に音源を完成させてきた」「複数人のプロジェクトをまとめていた」など、音楽を通じて身についた力をリストアップしてみましょう。
こうしたスキルは、“職務経歴書”に書くときの大事な材料になります。特にフリーランスやバンド活動をしていた方は、「職歴がない」と思い込まず、自分がしてきた実績を数字や具体例でまとめておくと、転職先にも伝わりやすくなります。
転職エージェント・キャリア相談の活用
「どんな業界が合うのかわからない」「そもそも何から始めたらいいの?」という人は、転職エージェントやキャリア相談サービスを使うのがおすすめです。プロに相談することで、自分では気づいていなかった強みに出会えたり、思ってもみなかった業界を紹介してもらえることもあります。
たとえば、音楽業界経験者向けの転職支援サービスや、異業種転職に強いキャリアカウンセラーを活用すれば、より現実的で納得感のある道を探すことができます。無料で相談できるところも多いので、「一人で悩むより、まず聞いてみる」くらいの気持ちでOKです。
音楽業界を辞めるか迷ったときの判断軸
「音楽を辞めたら、人生が終わるような気がする…」「逃げだと思われたくない…」そんな気持ちで、苦しい中でもがんばり続けている人も多いのではないでしょうか。でも、無理をして続けることだけが正解ではありません。辞めることは決して“負け”ではなく、“次のステップ”に進む選択でもあるんです。
ここでは、音楽業界を辞めるかどうかを迷ったときに参考にしたい「判断軸」を紹介します。大切なのは、他人の目ではなく“自分自身”の気持ちや未来を基準に考えること。あなただけの「正解」を見つけるヒントになれば幸いです。
「辞めたら負け」ではない。自分軸で考えよう
「あの人は続けてるのに、自分だけ辞めるなんて…」そんなふうに、比較や世間体で気持ちが揺らぐこと、ありますよね。でも、音楽業界はマラソンではなく、それぞれの“生き方”を選ぶ場。誰かと同じ道を歩く必要はないんです。
辞める=夢を諦めた、負けた、という考え方に縛られてしまうと、自分の本当の気持ちを見失ってしまいます。実際には、辞めてから新しい道で輝いている人も多くいます。自分が「どうありたいか」に素直になることが、最も大切な軸なんです。
夢を諦めること=終わり、ではない理由
「夢をあきらめたら自分じゃなくなる」そう思う気持ちもわかります。でも、夢を一度手放すことは、決してあなたの価値が消えることではありません。それどころか、視野が広がり、新しい夢や目標に出会えるチャンスになることもあります。
たとえば音楽を辞めたあとに出会った仕事で、「音楽より向いているかも」と気づくことや、「別のかたちで音楽と関われるんだ」と思える場面に出会う人もいます。夢に固執して心や体が壊れてしまうよりも、柔軟に方向転換することの方が、長い目で見て豊かな人生になることもあるんです。
辞めても音楽は続けられる時代
今は、音楽を“仕事”にしなくても続けられる時代です。副業で楽曲を配信したり、趣味としてYouTubeやSNSで発信したり、地域のイベントで演奏したり──音楽との関わり方は、仕事だけじゃないんです。
むしろ、仕事にしないからこそ、プレッシャーや収益に縛られず「心から音楽を楽しめる」人もたくさんいます。辞める=音楽から離れる、というわけではありません。あなたのペースで、あなたらしい音楽との関わり方を見つけることも、立派な選択肢のひとつなんです。
今すぐ辞めるべきケースと、留まるべきケース
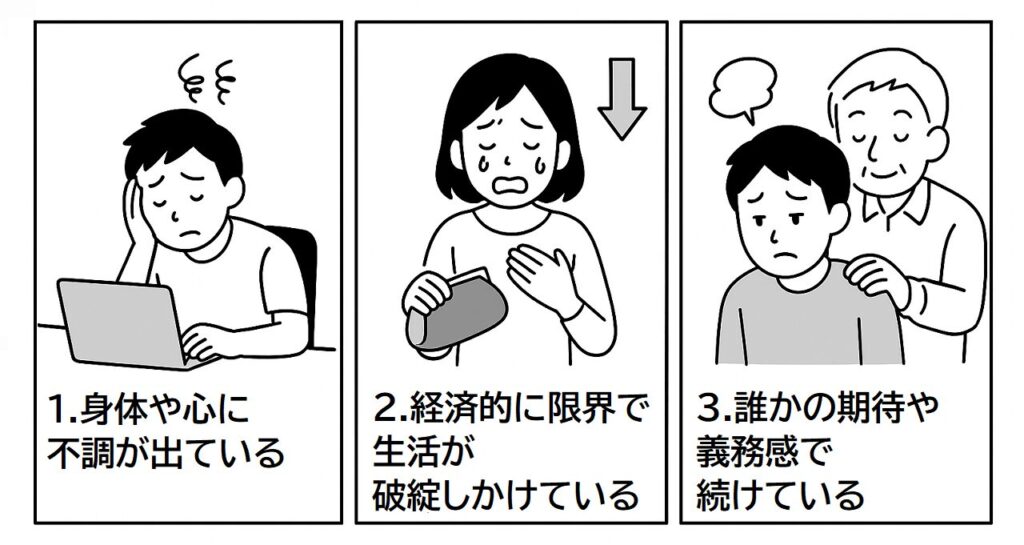
「続けるべきか、辞めるべきか」──この問いに明確な答えはありません。でも、状況によっては“今すぐ辞めるべきタイミング”というのも確かに存在します。自分の状態を冷静に見つめながら、「もう少し頑張るか」「ここで一区切りつけるか」を判断する目を養うことが大切です。
- 身体や心に不調が出ている
- 経済的に限界で生活が破綻しかけている
- 誰かの期待や義務感で続けている
身体や心の不調が出ている
眠れない、食欲がない、気分が落ち込み続けている──それはもう「限界のサイン」です。無理して続けるほど、心身のダメージは深くなります。音楽は続けられても、健康は取り戻せないこともあるからこそ、「体を壊してまで続けるべきではない」と覚えておいてください。
生活が破綻寸前になっている
家賃が払えない、借金が膨らんでいる、光熱費すらギリギリ…。こうした状況に追い込まれてまで音楽を続けるのは、本人にも周囲にも大きな負担となります。まずは生活を立て直す。そのうえで、もう一度音楽と向き合うほうが、結果的に良い形で再スタートできることが多いです。
客観的に「あと少し続ける価値」があるとき
一方で、「辞めるのはまだ早いかも」と感じるケースもあります。たとえばコンテストで入賞した、業界関係者から声がかかっている、フォロワー数や再生回数が伸びてきているなど、具体的な成果や反応が出ているとき。それは“次の一手”に向けたタイミングかもしれません。
ただし、続けるにしても「どれくらいの期間」「どの程度までやるか」を事前に決めておくのがおすすめです。ダラダラと続けると、気づけば何年も同じ場所で悩み続けてしまうことに。期限を区切って行動し、結果が出なければ次に進む。そんな勇気も大切です。
まとめ:夢と現実の間で、自分にとって最良の選択を
音楽業界は、美しくも過酷な世界です。「好き」という気持ちだけでは続かない場面も多く、理想と現実のギャップに悩む人は少なくありません。けれど、「やめとけ」と言われる一方で、それでも続けて成功している人がいるのも事実です。
大切なのは、自分自身にとっての“幸せな音楽との関わり方”を見つけること。辞めてもいいし、続けてもいい。どちらを選んでも、それはあなたにしか歩めない道なのです。誰かの正解ではなく、自分の人生にとって納得できる選択をしていきましょう。
よくある質問(Q&A)
- 音楽業界を辞めたらキャリアは終わりですか?
-
いいえ、終わりではありません。音楽業界で培ったスキルや感性は他業種でも活かせます。ITや教育、福祉、マーケティングなどへの転職例も多数あります。
- 音楽を辞めても続ける方法はありますか?
-
もちろんあります。副業や趣味として音楽を続ける人も多く、今はサブスク配信やSNS投稿、地域活動など、収益に縛られず楽しめる環境が整っています。
- 音楽業界を辞める判断に迷ったときはどうすれば?
-
心や体に不調がある、生活が破綻寸前、もしくは「自分の意思より周囲の期待で続けている」状態であれば、一度立ち止まって見直すのがおすすめです。キャリア相談を活用して客観的に判断するのも良い方法です。

辞めるか続けるかは、誰かが決めることじゃないよ。あなたが「自分の人生をどう生きたいか」で決めてOK。音楽の夢も、人生の選択も、もっと自由でいいんです。











